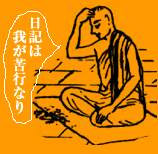
Jain Diary:ジャイナ日記
「一日一ジャイン」をモットーにはじめたものの、「飲み会と更新をどう両立するか」に苦悩する毎日。そんなヒマがあったら他のコーナーを充実させるべき、という声も多い。
75.文字ぎらい
ぼくはもともと文字ぎらいであった。幼少のころはいわゆる知恵遅れというやつで、同い年のやつらが歌っているころでも、言葉が満足に出てこない状態であった。小学校になってからもその差は縮まらず、みなが漢字で自分の名前を書いているのに、ぼくはいつまでたっても、ひらがなしか書けなかった。
習字の時間はまさに地獄であった。左利きの私に、先生はむりやり右で書かせようとする。それも無理はない。漢字はもともと左手で書くようにはできていない。もっと大胆にいえば、左利きのヤツは文字を書くな、と文字そのものがケンカを売っているようにみえた。文字はつねに、劣等感の対象そのものであった。
高学年になっても、みなが授業をしているときに、ぼくは机を離され、バケツに水を汲んでは風景画を描いていた。クラスのみんなが国語の授業をしているとき、水を汲むためにクラスメートたちの前を横切っていた。(2004.01.21記)
74.散歩
会社を辞めてからよく散歩している。
だいたい毎日2時ごろまで仕事して、そのあと二駅ほど歩いて昼飯を食いに行く。いつも鞄に雑誌2冊くらいいれといて、食後にお茶を飲みつつページをめくる。
帰りは大きな本屋さんに行く。ついつい買ってしまう。
こないだは趣向をかえて銭湯に行ってみた。露天風呂があるいま流行りのつくりである。
3時ころだったが、けっこうなにぎわいだ。
「この人たちはいったい何を生業としているのか」
と考えてしまったが、それはお互いさまというものであろう。
アパートの隣の人がこれから採用面接だという。一年ほど前にリストラされて、その後も決まらずじまいだった。やはり中高年の再就職は並大抵ではないらしい。
「決まったらお祝いしよう」と約束し、送り出してやった。
うまくいったかな。今日はこっちもソワソワしっぱなしだ。(2004.01.20記)
73.Jain Art更新しました
ひさびさに日記じゃないページを更新。シッタンナバサル石窟寺院フレスコ画の写真です。日本ではいうにおよばず世界的にみても超レアーだと思いますのでぜひご覧下さい。未完のまま残されたウプサラ(天女)の素描が美しかったのを思い出す。図版の順番がメチャクチャだけど、まずはアップということでご勘弁を。しかもダブリまくり。(2004.01.20記)72.情報
情報は、電子化によって本来の「弱さ」を身につけつつある。それは、不完全さではなく、柔軟さに似たものだ。これまでインクの粒子に封印され、変化することを禁じられた情報が、電気の粒子のままで配布されることで、流れる水のごとく形を変え、常に動き続けることができるようになった。
これによって、個々の情報はもっとあいまいで、正確さに欠け、信頼性のないものになるだろう。しかし、それぞれの情報が不完全さを基調としながらオブジェクトとして互いにメッセージを交換し、響きあいながら変容していくという構図は、いわば生命活動と言い替えてもいいものである。もともと情報理論は生物理論をもとに発展したのであるから、現代の状況はその結果でしかないのであろう。
情報(生物)は常に生命圏を形成しようとする。情報の電子化はわれわれが望んでいるのではなく、情報が望んでいるのだ。「はじめに情報ありき」。情報が受肉せずに存在できるということは、とても霊的な問題であるともいえる。情報の身体離脱。
これからの情報は不完全さをむしろ基礎条件として動き出すだろう。完成したから出すのではなく、不完全さを永遠に修正していくような情報とのつきあい方が生まれる。オブジェクト指向のやろうとしていることもこれなのだ。つまり、不完全さまでも完全に写像することなのである。世界をあるがまま電子空間に投影すること。(2004.01.19記)
71.料理人
「詩人は、その詩句を、心ゆくまで彫琢することができる。また、作曲家は、ハーモニーが気に入らなければ、その小節を線で消すことができる。そして、画家も、気に入らない色の上に、別の色を重ねることができる。しかるに、料理人は、手直しをすることも許されず、いささかの猶予も与えられない。今か今かと待っているお客さんに、少しの遅れもなく料理を出すのが、彼のつとめである。したがって、料理人が、その仕事を全うしようとするときに要求されるのは、偉大なる芸術家の持つ知性と感性、加えるに、総司令官の素早い読みと、何事にも動じない冷静沈着さとである。」(グリモ・ドゥ・ラ・レニエール)(2004.01.18記)70.「15分」
「扉は開かれ、この15分間に、私は何年も大学で学ぶ以上のことを見、また知った」とドイツの神秘家ヤコブ・ベーメは語っている。『ヤコブ・ベーメ』(P43)
15分で悟る人もいるのだから、たかが15分とバカにできない。「ひと仕事」の単位としては、充分な資格をもっているといえるであろう。(2004.01.17記)
69.信仰
「アフリカ史」にその名を残す、偉大なる皇帝メリネク三世は、いわば近代エチオピアの父ともいうべき人物である。しかし彼には、実に奇妙な癖があった。体の調子の悪いときには、きまって「聖書」の数ページを食べた。そうすれば必ずもとのいい状態にもどると信じて疑わなかったのである。
一九一三年の十二月、彼は脳卒中に襲われた時、「列王記」全編を食べてしまった。そして、死んだそうだ。(出典不明)(2004.01.16記)
68.眠り、夢
自分の時間を切り売りするなら、どの部分を売るべきだろうか。マグロにたとえれば、まずトロの部分は自分の好きなことをやるのに必要な美味しい時間といえるであろう。睡眠時間は、いちばんムダで食えない時間に見えるので、ちょうどホネの部分といったらいいかもしれない。だけども、ホネは食えないが、ないと肉のつく場所自体がなくなってしまう。「無用の用」というやつだ。骨太に生きるには、まず睡眠を充実させねばならないだろう。そうすれば人生の肉付きもよくなるというものだ。ホネまでしゃぶるとは、まさに眠りをむさぼることである。
それでは、どうやって睡眠を充実させることができるだろう。よく夢の効用をとく人がいるが、そんな人は白昼夢に悩まされる。逆に夢のない、意識が消失するほど深い眠りをするひとは、覚めてる時間がすべて夢になっている。ぼくはそっちのほうがいい。夢をみるよりも、夢に生きたい。(2004.01.15記)
67.編集とは?
何を集めるのか? コトノハを集めるのである。
何を編むのか? 関係の糸を編むのである。
言葉の編み物
「仏典結集」−スートラ
ハイパーリンク
言葉には二種類ある。「ことのは」と「こと」である。ことばを叙述したものが「こと」。言魂になる。古代日本人にとって大事だったのは叙述であって、単語ではなかった。この叙述を「いふ」「かたる」「つげる」から「書く」へ。
「ことのは(言葉)」−かたこと(片言)。動きが与えられる−まこと(真言−マントラ)。方向が与えられる。つまり、「主体」と「動作」、つまり静と動が一体になること。
EDITはGIVE OUTのこと。語源は EDERE−EDO。日本古代で「EDO」にあたるのは、おそらく「ムスビ」。「産霊」という言葉をあてた。ムスビはもちろん結びを意味した。
編集とは、カタコトを関係の糸で「編み」、それを「集」成し、マコトにすることである。この行為がムスビ(産霊)。「文章を結ぶ」「結論」「結びの言葉」。お結び。
宗教−RELISION−語源relegere−結ぶ、縛るの意味−。
ヨガ− Yoga −結ぶの意味。
言葉の受肉。
言霊信仰。
論理(ロジック)−言葉・理性(ロゴス)−レゲイン(集める)
リ−ズン(理性)。理はことわり(事割り)。言割り。
欧米で「THE WORD」といえば、神を意味する。
「初めに言葉(ロゴス)がおり、言葉は神と共におり、言葉は神であった。この方は初めに神と共にいた。すべてのものは彼を通して存在するようになり、彼を離れて存在するようになったものは一つもない。」(ヨハネ福音書1−1、2、3)
アフリカのドゴン族の神話によると、創造主アンマは、記号を書くことから創造をはじめる。アンマは八種類の穀物の種子を作るのだが、これらの種子は、八つの言葉の証拠または象徴だと解されている。(『青い狐』せりか書房)(2004.01.14記)
66.なぜ?
哲学および数学の諸問題、命題は、まさに言語そのものの構造から増殖するカビのようなものか。答えることのできる問題よりも、答えられない問題のほうが常に多いのはなぜか? なぜWHYはBECAUSEよりもおしゃべりなのか? この問いもまたWHYのひとつになってしまうのか?(2004.01.13記)65.知ること
動物や植物だって、人間と同じくいろんなことを知っている。食べちゃいけないものや、天敵からの身の守り方とか、生まれながらにして必要なことは何でも知っている。必要になれば、学習だってするし、知識もためこむ。しかし彼らは、知っていることを知ることができるかといえば、ノーなんじゃないか。メタレベルで知の風景を鳥瞰できるのが人間の存在証明であり、また人間ゆえの孤独を生む原因でもある。(2004.01.12記)64.もっと魚をとりたまえ
ニューヨークに住む裕福な企業家が、コスタリカの海辺の町へ二週間の休暇を過ごしに出かけた。彼は現地に到着したその日に、地元の漁師から買った魚の、えもいわれぬ味わいにすっかり見せられた。
翌日、波止場でふたたび漁師と出会ったが、その日の獲物はすでに全部売り切れていた。
どうやら漁師は、とびきり上等の魚が大量に獲れる穴場を知っているらしいが、一日に獲るのは五尾か六尾に決めているという。
なぜもっと熱心に働いてたくさんの魚を獲らないのかと、企業家は尋ねた。
「そうはいっても、だんなさん」と漁師は答えた。
「今の生活なら、毎朝九時か十時までのんびり寝ていられるし、そのあとは子供たちと遊んで、それから一、二時間ばかり漁に出ればいい。午後は一時間か二時間ほど昼寝して、夕方は早めに家族全員でゆっくりと晩飯が食える。それで夜になったら村へ繰りだして、仲間とワインを飲みながら、ギターを弾いたり歌を唄ったりして、毎晩楽しく過ごせるんですよ。やりたいことをやって何不自由なく暮らしているのに、これ以上何が必要なんです?」
企業家はいった。
「もっと魚を獲りたまえ。そうすれば、きみの未来はばら色だ。いいかね、わたしはニューヨークから来たビジネスマンだ。きみの人生が今よりもっとすばらしいものになるように手を貸してあげよう。何を隠そう、わたしはハーバードでMBAを取得した経歴の持ち主だ。ビジネスやマーケティングに関して知らないことは何ひとつない」
さらに調子に乗ってつづけた。
「バラ色の未来を実現させるには、まず、毎朝早起きをして夕方まで漁に励み、夕食後また漁に出ることだ。そうすれば、あっという間に金がたまって、もっと大型の船に買い換えることができる。二年もしたら、五、六隻の漁船を所有して、仲間の漁師たちに賃貸しできるようになる。それから五年もすればきみのもとに集まる莫大な量の魚を加工するための工場を持てるし、なんなら独自のブランドを立ち上げることだって可能だ。」
漁師の困惑した表情を尻目に企業家は言葉を継いだ。
「さらに六、七年したら、ニューヨークでもサンフランシスコでも好きな都市に移り住んで自社製品の営業に専念し、工場は誰かに任せればいい。十五年か二十年もしっかり働けば、大富豪になるのも夢じゃない。そうなったら、あとは死ぬまで一日だって働く必要はないんだぞ」
「そしたら、何をすればいいんです?」
「そしたらメキシコかどこかの小さな村に移り住むことができるよ。毎日のんびり朝寝を楽しみ、村の子どもたちと遊んで、午後はたっぷり昼寝をして、ゆっくりと夕食をとって、夜は仲間とワインを飲みながら、ギターを弾いたり歌を唄ったりして、毎晩楽しく過ごせるじゃないか」(2004.01.11記)
アーニー・J・ゼリンスキー著 前田曜訳『ナマケモノでも「幸せなお金持ち」になれる本』英治出版
63.骨折り
数日前に歯医者に行ったら「奥歯に病巣があります」といわれ治療することになった。その時点ではなんともなかったのだが、夕方ころ芥子漬けをつまんでいたら猛烈に腫れだした。誰でもみな経験がおありだろう、こんなときはただ激痛に身悶えるしかない。翌日すぐさま病院に行き、腫れ上がった患部を切開して内圧を下げる処置をしてもらった。麻酔やら点滴やら計4本の注射をされてやっと解放されたが、帰りがけトイレで鏡をみたら左の頬だけ宍戸錠である。これでは人前に出るのも億劫になるというものだ。
しかし、こんなときにかぎって人前で何日も話すような仕事が入ってくるから不思議なものである。「人生において、あらゆるものは同時にやってくる」というのが書き手のモットーなのであるが、その同時にやってくるものは、互いに矛盾してるというのもまた経験上明らかなことだ。
こういった場合、どちらかを捨てて片方のみを選択する、つまり一匹を追うのは誤りではないか。どんなに骨折りであろうともやはり両者をこなすべきであろう。なぜなら、どっちかが落ち着いたらもう片方を、と考えたりするとたいていどちらもうまくいかないからである。
たしかに両者を同時にこなすというのは最も勇気のいる選択ではあるが、最も易い道であるともいえる。同時にやってくるものは、また同時に去っていくものだ。これらをどうにかやり終えた人にしか味わえない幸福感というものが、この世には確かに存在する。度重なる骨折りには、それに続く平穏な日々という報酬が支払われるのである。(2003.11.02記)
62.無題
ボンディ 書くのは好きですか?
シオラン 嫌いですね。それに私の書いたものは、ごくわずかです。たいてい、私は何もしていない。私はパリで一番ひまな人間で、私よりひまな人間といえば、ま、客のつかない売春婦くらいのものでしょうね。
ボンディ 生活費はどうしているのですか。
シオラン 四十になるまでソルボンヌ大学に籍を置いていて、学生食堂を利用していました。一生こういう状態がつづいてくれればと願っていたのですが、二十七歳以上の在籍を禁ずる法律ができましてね、この楽園から追放されてしまったわけ。パリに来たとき、私はフランス学院に学位論文を書く約束をしており、論文のテーマ-ニーチェの倫理学に関するものです-も提出済みだったのですが、書く気などさっぱりなかった。その代わり、自転車でフランス全土を回りました。結局、奨学金は継続されることになりましたが、フランスを脚にたたき込んだことも評価できなくはないということになったのでしょう。
ボンディ あなたはよく反動家よばわりされていますね。
シオラン 私は反動家ではない、反動家以上ですよ。あるとき、アンリ・トマが私に、「きみは一九二〇年以降の事態にすべて反対なんだね」と言ったことがある。私は「いや、アダム以来だよ!」と答えましたがね。
シオラン著 金井 祐訳『シオラン対談集』p5-7 法政大学出版局 叢書ウニベルシタス586
(2003.10.15記)
61.金は時なり
時は金なり、―――という諺があるが、古今東西を通じてこれくらい卑俗な諺もあるまい。しかし、これを引っくり返してみると一つの貴重な真理がえられよう、いわく、金は時なり。私は昨今のような暗い、霧でかすんだ朝、二階の寝室から降りてきて、輝かしい炉火が書斎でパチパチと音をたてて燃えているのを見るごとに、そのことを思う。仮に私が貧乏であの楽しい炉の火を燃やす金もなかったとしたら、私のまる一日はどんなに変わったものとなるだろう。心の平静を保つのに必要な物質的な慰めがないため、どれくらい多くの日を私は今まで無駄に費やしたことか。金こそは時間なのだと思う。金があれば、私は時間を自分の好きなように買うこともできる。もし金がなければ、その時間もいかなる意味においても私のものとはならないだろう。いや、むしろ私はその憐れな奴隷とならざるをえないだろう。金は時間だ。ありがたいことに、この種の買い物をするのには金はわずかでいいのである。あまり多くの金を持っている人は、金の本当の用い方に関するかぎり、金をあまり持っていない人と同じく、生活は苦しいものなのだ。われわれが生涯を通じてやっていることも、要するに時間を買う、もしくは買おうとする努力にほかならないといえないだろうか。ただ、われわれの大多数は、片手で時間をつかみながら、もう一方の手でそれをなげ捨てているのである。
ギッシング作 平井正穂訳『ヘンリ・ライクロフトの私記』P273 岩波文庫
(2003.10.04記)
60.ジャイナ検索
ちかごろ仕事で多忙を極めていたが、クライアントの内部抗争のため一時中断。このすきに我がジャインワールドにも全文検索機能を搭載することにした。とはいっても中身は「Google フリー検索 (カスタマイズ版)」なので設置までたった30分ほどで完了。あっけないものであった。
ひさびさに映画を見た。「サラマンダー」は、ブロンド美人を残してアメリカ人が全員死ぬというものであった。マシュー・マコノヒーは準主役級の扱いだったが、最後の最後で竜に食べられてしまった。イギリス人やフランス人は生き残ったようだ。
エドワード・バーンズの監督モノは必ず見るようにしている。ハンサムだし脚本もいい。しかし最新作「サイドウォーク・オブ・ニューヨーク」にはちょっとがっかりした。彼の作品はいい意味で映像表現にアマチュアっぽさが残っていて好きだったが、だんだん作為を感じてきた。本作でも街頭インタビューをプロットとして巧く演出しているが、ドキュメンタリー風の素っ気ないカメラアングルが逆に鼻についてしまう。「自分はいま作り物を見ているのだ」というスピルバーグ映画につきものの感情をいだかずにはおれない。
観ていることを忘れるくらい、没入できる映画が好きだ。しょせん映画とて作為の産物であるが、スクリーンの上ではその臭いをさせてはいけない。(2003.10.01記)
59.泣き
ちかごろどうも涙もろくていけない。今日もジャイアンツ川相の引退に涙し、テレビドラマの再放送にまた泣いた。昨日も『ノッティングヒルの恋人』ごときでボロ泣きしてしまった。
歳をとると涙もろくなるというのは否定しがたい事実である。しかし、涙する理由は、歳とともに変化していくのであろう。若いころは悔しさ、寂しさ、悲しさで泣いたが、三十路もこえると悲しい映画を見ても「なんでこうなるの」とハラが立つだけだし、失恋しても憂鬱で無表情になるだけである。逆に、長年の努力が実を結んだり、仲間どうしが助け合ったり(書き手は特にこのネタに弱い)、ラブコメの幸福な結末には号泣するのであるが、みなさんはいかが。
泣きたいときに涙を押さえるのはたいへんなストレスになり、心身に悪いときく。逆に、よく泣くのは健康にたいへん好ましいそうである。吉幾三もよく泣く人だが、大酒のせいで相殺されているのであろう。(2003.09.14記)
58.むかしむかし
むかしむかしぼくがいた
すっぱだかでめをきょろきょろさせていた
いまのたいようとおなじたいようが
あおぞらのまんなかでぎらついていて
いまのかぜとおなじかぜが
くさのうえをさあっとふいていた
がっこうはなかったけれどぼくはいた
おもちゃはなかったけれどあそんだ
ほんはなかったけどかんがえた
はんばーぐはなかったけれどうんちをした
さびしくなるとなぜかわからずにないた
おかしいときはなにもわからずにわらった
おなかにあるおへそがふしぎで
いつもゆびでさわりながらねむった
そしてゆめのなかではへびのあめがふり
ぼくはうまれたりしんだりした
むかしむかしどこかにぼくがいた
いまここにぼくがいる
谷川俊太郎詩集『はだか』より
57.数覚をもつということ
そもそも数学的な美とは、そのネイキドさにある。贅肉をそぎ落としたシンプルな数式ほど、それはイデアにつうじており、理想世界の言語に近づいている。イタリアの哲学者ヴィーコはいう。
数学的真理は裸であってもいいが、人間の世界で真理は裸であってはならない
たしかに人間は肉をまとっている以上、ヴィーコがいうように純理では割り切れない存在であろう。それを知ってもなお、純粋に霊を裸にしようと奮闘するのがジャイナのジャイナたる所以なのである。
数学者というのは、いちばん明晰で現実的なことを考えているようで、実はほとんどみなプラトン学派だ。だいたいにして、証明できるかどうかにかかわらず、解は存在するとか、神はご存じだとか考えること自体、プラトニスト以外のなにものでもない。「不完全性定理」で知られるゲーデルなどは、二十世紀最大のプラトニストであろう。現代のルイス・キャロルといわれる論理学者レイモンド・スマリヤンは、彼のことを「数学的現実主義者」と共感をこめて描写している。もちろん本人も絶対なるプラトン学派を自認してやまない。
彼らは数という「非現実の現実」に生きる人々なのだ。「怠け数学者の記」のなかで小平邦彦名誉教授は、この数を実体視するプラトニスト感覚を「数覚」とよんでいる。
数学を理解すると言うことは、実在する数学的現象を「見る」ことである。「見る」というのは数覚によって知覚することである
数が「実在する」という言葉を事前のこととして語っているどころか、それを「見る」というのだから、教授もバリバリのプラトニストだ。
聴覚によって音楽を楽しむように、数覚によって数学を楽しむ。まるで「ガリバー旅行記」にでてくるラピュタの住人たちみたいだ。魂の数学者たるマハーヴィーラも、やはりそんな皮膚感覚をもつ人だったのだろうか。
インドでは人類の始祖を「マヌ(manu)」というが、渡辺昇一氏の知られざる名著「英語の語源」によると、これは英語の「人間(man)」と同じく「men-(考える)」が語源であるという。さらに「数学(math)」(*)も、やはりこの「men」が語源となって派生したという。つまり、アーリア人やギリシャ人などのインド・ヨーロッパ語族にとっては、数を数え、思索することが、そのまま人間の存在証明になっているのである。
ジャイナの教理も、そんな印欧の人間観が底になっているのかもしれない。ニガンタ教はパールシヴァまで綿々と伝わったインド古来のものだろうが、マハーヴィーラは、それをインド・ヨーロッパの明快な論理で整備することにより、ジャイン・ダルマに更新したのではないだろうか。ちょうどユダヤの地方宗教にすぎなかったキリスト教が、聖パウロのおかげでギリシア的な明快さを身につけたように。(2003.09.08記)
(*)インドでは学院をmath(マート)という。これも同根であろう。
56.数なるゆえに、われ信ず
ブッダの教えが詩であるなら、マハーヴィーラのは数式だ。
ジャイナは道理よりも、純理でダルマをつかまえようとする。その思索スタイルはまさに数学者のそれに近い。シュラヴァナ・ベルゴラの高僧チャルキールティ・スワミ・ジーはいう。
数は純粋なる抽象表現にすぎない。だから特定の実体にとらわれることがない。よって全実体の考察に適用できる。
万物は数である、とは言ってないが、万物の尺度になりえるのは数しかない、とハッキリいいきっている。言語としての数の適用だ。このようにジャイナはまずお坊さんからしておよそ宗教者らしくない。研究室にこもりっぱなしのプラトニスト、といったイメージである。
中世インド数学の担い手も、じつはジャイナであったという。ジャイナ経典「アヌオーガッダーラ(三世紀)」には、種々の数理が展開されているが、なかでも白眉なのは「無限」の考察だ。かれらは無限集合に「限定無限・固有無限・無限的無限」の三つの規模を数えるという、現代数学ばりのセンスをみせていたのである。
古代ギリシアの数学者たちは、多くのパラドックスを生じさせる「無限」という概念を、できるだけ数理から追い出そうとした。それゆえ鬼才カントールが無限集合論を完成するまでの約二千年、西洋において無限は「数」と認められていなかった。いっぽう未熟ではあるが、ジャイナは三世紀にして「無限」を数理におさめていたということになる。
マハーヴィーラの教えを数学的に再構築し、ちゃんと公理をたてて論証する。現代にはそういう律義なジャイナもいたりするから驚きだ。もしマハーヴィーラがいま生きていたら、そんな信者たちを思ってパソコンの所有はいいよ、と説くかもしれない。
インド人はゼロを発見した民族だ。現在、その末裔たちはシステム・エンジニアに衣替えして、その優秀さを世界にみせつけている。おそらくインド人には、天賦の数学センスがあるのだろう。数学者ラマヌジャンを生んだ実例もある。それに抽象思考にめっぽう強いところは、彼らの宗教からもイヤというほどうかがえる。いずれインド産のどえらいコンピュータソフトが生まれるかもしれない。「ブラフマン」なんていうサイキック・ソフトが登場するのではないか。
ちかごろ日本でも、インド医学「アーユル・ヴェーダ」がもてはやされるようになった。この医学の基本原理は、「サーンキヤ」といわれる思想をベースにしている。サーンキヤとは、もともと「数える」という意味であり、転じて純粋哲学をあらわすようになった。精神原理と物質原理の開展から万物が生じたとする、二元思考がこの哲学の特徴だ。また「バガヴァット・ギーター」のなかでクリシュナも、みずからの叡智をサーンキヤと呼んでいる。どうもインド人は、真理を「数える」民族らしい。
こうしてみると、我々が日頃「宗教」というばあいと、インド人が宗教の意味でつかう「ダルマ」には、かなりニュアンスにへだたりがあるような気がする。「秩序」や「原理」がない不合理な思想を、決してインド人はダルマといわないのだ。
「不合理なるがゆえに、われ信ず」といったのは、教父テルトリアヌス。主知主義をもって鳴るジャイナがきいたら、さんざんコキおろしそうなセリフではある。(2003.09.07記)
55.ピタゴラスと豆
マハーヴィーラは七種の線、五種の幾何学図形を発見した人物だと伝えられている。これはピタゴラスを連想させるプロフィールだ。ジャイナは神秘思想に無縁だったが、数の神秘は別だったらしい。
ピタゴラスというと「三平方の定理」が有名だが、輪廻転生も説いていたといえば、ぐっとインド臭くなるであろう。彼の輪廻説によると、霊魂は空中に漂っており、時がくればあらゆる生物の胎内におもむくという。馬、ロバ、ねずみとして生まれた霊魂は、また転生して人間のなかに舞い戻る。よって家畜はおろか、ハエなどの昆虫にいたるまで、すべての動物を殺すことは殺人にもひとしい。このように彼は生類の不殺生を説き、生涯ベジタリアンで通したという。
それだけではない。彼はそら豆などのマメ科植物を決して食さなかった。なぜなら「人間とマメ」は、同じ腐敗物から生まれた兄弟同志である。それゆえ、そら豆を食することは、これまた殺人になると考えたのだ。
ジャイナの上をいくこだわりようである。確かにマメ科の植物というのは、「畑の肉」とよばれるほどタンパク質に富んでいる。『はるかなる視線』のなかで人類学者レヴィストロースも、豆を禁忌する民族が確かに存在することを示している。しかし皮肉にも、そのマメがピタゴラスの命を奪うことになった。
彼の教団は市民の人気が高く、権力者の恨みを買うことが多かった。そのためピタゴラスは迫害者の手から逃れようとするのだが、ゆく手を豆畑によってさえぎられてしまう。この畑をこえなければ殺される。しかし彼は豆を踏みつぶすより、みずから死ぬほうを選んだのである。ついに迫害者は、この風変わりなヴェジタリアンの命をうばった。
これが有名な、「ピタゴラス、マメ畑に死す」の逸話である。これについては寺田寅彦が「ピタゴラスと豆(昭和九年)」と題して味わい深い文章を残している。
ピタゴラスと豆の話は、現在のわれわれの周囲にも日常頻繁に起こりつつある人間の悲劇や喜劇の原型であり雛形であるとも考へられなくはない。色々の豆のために命を落とさないまでも色々な損害を感受する人が中々多いやうに思はれるのである。それを褒める人があれば笑ふ人があり怒る人があり嘆く人がある
禁を犯すより、敵の手にかかって死んだほうがましと決めて、ピタゴラスは豆畑に散った。寺田寅彦が語るように、純粋者の生きる道筋は悲劇と同時に、喜劇でもあるといえるのではないか。つまり、第三者からみればまさしく「バカげた行為」だということだ。
餓死したヴェイユ、ゲーデルといい、数学者カントルといい、「純粋の豆」に生きた人の最後は、ピタゴラスのように哀しい滑稽さがある。それは現世をあるがままで受け入れることを拒絶した人間の、ぬぐいがたい最後なのだろうか。純粋な狂気を甘受できるのは、ただ死だけなのだろうか。(2003.09.06記)
54.裸の男の子
マイスター・エックハルトはひとりの美(うるわ)しい裸の男の子と出会った。
そこで師はこの子にどこから来たかたずねた。男の子は答えた。「神のところからやってきた。」
「どこに神を置いてきたのかい」
「徳のある心の内に」
「どこへ行きたいの」
「神のところへ」
「神はどこで見つけるの」
「すべての被造物から離れたところ」
「君はいったいだれ」
「王」
「君の王国はどこ」
「心の内」
「誰かにふみこまれないよう気をつけなさい」
「そうするよ」
そこで師は男の子を彼の部屋につれてゆき、語った。「どれでもいいから好きな上着を取りなさい」
「そんなことしたら王でなくなってしまう」
そう語って男の子は姿をかき消した。
それは神自身であった。神はわずかの間であったが、マイスター・エックハルトと共に過ごしたのであった。
田島照久編訳『エックハルト説教集』P263 岩波文庫
53.アレクサンドロスとジャイナ
紀元前四世紀ごろインドに侵入してきたアレクサンドロスの一行なども、極度の禁欲を旨とするジャイナ僧にはかなり驚嘆させられたようだ。いくぶん興味本位から、彼はダンダミスというジャイナの指導者を西洋へ連れ帰ろうと説得を試みるが、ダンダミスはただ、「なぜかくも遠くまで旅行するように望まねばならなかったか」と彼に尋ねたという。
かれはアレクサンドロス自身と同様に神の子であり、すでに所有物は満ち足りているので、アレクサンドロスから何も望まないと答えたといわれる。海や山を越えてかくも遠くまで指揮官に従ってやって来た人々は、その放浪に際限がないように思われる限り、それから何らの利益を得る所がなかったと彼は見た。それ故にかれは、アレクサンドロスがかれに与えうるものは何も欲しなかったし、また他方、かれを強制しようと企てなされるかもしれないことは、何も欲しなかった。かれが生きているかぎり、インドは季節相当の果物でかれが必要とする一切を供給した。そして彼が死んだ時に、かれは気の合わない伴侶、すなわち、かれの身体から、自由になるであろう
『古代インドとギリシア文化』ジョージ・ウッドコック著 ; 金倉円照,塚本啓祥訳注. 平楽寺書店, 1972
なんだかディオゲネスの有名なエピソードの焼き直しという気がしないでもないが、こと思想面に関しても、インドの哲人たちは「野蛮人たち」から何も(天文学以外は)欲しなかったという。逆に、ギリシア人の側にはインドの思想に感化されたものは少なからずいたようで、当時アレクサンドロスの従者であったピュロンというソフィストなど、西北インドの都タクシラにおいてジャイナ僧と対話を重ね、その哲理を「懐疑主義」という形に翻訳してギリシア哲学にプラグインしてみせたという説もある。その後デカルトをはじめとする西洋哲学への影響ぶりはご存じのとおりである。
さて、このようにインドの外には無関心と思われるジャイナだが、現代においては布教活動のために乗り物をよく利用するし、アメリカでもフィリピンでも、頼まれればどこでも出かけていく。しかし一方で昔気質なジャイナたちは、徒歩以外の移動手段に頼ることを頑なに拒んでいる。神話は生きているのだ。(2003.08.25記)
52.二読三読
ちかごろ就寝前、布団にうつ伏せになり、マーカーを握りつつヒルティの『幸福論』を二読三読するのが誠に楽しい。この本はタイトルに似合わず仕事の仕方、時間の使い方についての至言に充ち満ちており、何度となく読んだはずなのに、ページを開くたびにまた新たな発見がある。語り口のゴツゴツしているところなど、マルクス・アウレーリウスを彷彿とさせて大好きだ。ブックオフでまとめ買いしたにもかかわらず、いまだに第1巻から抜け出せないでいる。おそらく一生無理であろう。
小生は多読ということができない性格で、同じ本を何度も読み返してはその度に感動しているというなんともオメデタイ人間である。音楽にしても同様だ。モーツアルトやスティーリー・ダンを毎日聴いても飽きるということがない。
ジャイナもまた、ヒルティと同じく興味がつきることはない。その想いが高じてホームページなどを運営してはいるが、私にとっては布団にうつ伏せになりつつ赤線をひっぱっているのと同じ気持ちでやっているにすぎない。いくらか箱庭的ではあるが、それでもGoogleにはちゃんとヒットするし、微力ながら日本人のジャイナ理解に貢献していると私は信ずる。
しばらくの間、ダルマのページからこぼれ落ちた雑文の受け皿として、このページを使わせていただく。「なんか前に読んだことあるなあ」という方もおられると思うが、そのまま読み飛ばしていただきたい。(2003.08.24記)
51.自殺行
一九五五年・九月一八日。マハラーシュトラ州の聖地クンタラギリにおいて、ある年老いたジャイナ僧が自殺した。
彼は空衣派の指導者であり、名前はシャーンティサガラ(平和の海)。三五年にわたる修行生活のラストに彼が選んだのは、二五○○年前にマハーヴィーラが行ったのと同じ、「自殺行」であった。
彼は無一物だった。下履きさえまとわず、インドじゅうを裸形で遊行していたという。一日に一回だけ布施をうけ、手を椀にしながら彼は食事をした。ことばを語るのは日中だけで、日没後は死人のように寡黙であったという。
そして、ついに自殺行がはじまった。八月一四日から九月七日までの一ヶ月弱、彼は水しか受けとっていない。七日からのちは空気だけ、つまり完全な断食に突入した。
そして九月一八日未明。確とした意識のまま、シャーンティサガラは祈祷を唱えつつ、みずからの呼吸を断ったという。
信じられないが、これは事実だ。彼らのあいだには自殺マニュアルさえ伝えられているのである。「岩波講座―インド思想I」より、その部分を引用しておこう。
修行者は、いよいよその時がきたことを悟ると、資格があるかどうかを試した後、村や森で敷きわらをもとめ、生き物がまったくいない閑所に場所をさだめる。そこで四肢と身体の動き、歩行を放棄し、食を断って禅定にはいる。
そこから死にいたるまでは、次のような三タイプに区別する。
- 徐々に食を減らしていって、最後にまったく食を断って死をむかえる。
- 次にすぐれたもので、用便とか、疲労を除くために歩くとか、身体を伸縮する(要するに背伸び)とかを除き、じっと座したまま死をむかえる。
- 最もすぐれたもので、一切の身体の動きをやめ、坐からまったく動かず、断食して一切の執着をはなれ、死をむかえる。
これはのちに自発的な死とか、賢者の死とか呼ばれるものであるが、修行者はこの三つの解脱法、すなわち「死にかた」のどれかを選ぶことになる。これは三昧死ともいわれており、ジャイナ教では後世まで重視され、賞賛された最後である。ジャイナのいう精進とは、この三昧死のことを意味し、これこそ勇者の資格とみなされた
ジャイナは死にざまに異常な感心をそそぎ、修行の究極は断食死であるとさえ豪語する。飢餓自殺の物語のみを集めて、編集した経典もあるほどだ。(2003.08.24記)
