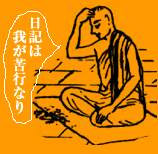
Jain Diary:ジャイナ日記
「一日一ジャイン」をモットーにはじめたものの、「飲み会と更新をどう両立するか」に苦悩する毎日。そんなヒマがあったら他のコーナーを充実させるべき、という声も多い。
50.グジャラート州とジャイナ
インド人とお酒ほど不釣り合いなものはない。
そんな彼らも西洋文明にすっかり毒されたのか、近ごろではどの州でもたいがい酒はおくようになった。南インドのタミル・ナードゥ州など、リカー・パーミットなしでは旅行者でさえ一滴も飲めなかったというのに、いまでは酒屋がどやどや軒を並べているという始末だ。
イーデス・ハンソンさんの「インド片恋い」を読んでいたら、グジャラート州アーマダーバードに住む彼女のお兄さん夫婦に、こっそりウィスキーを差し入れする場面があった。グジャラートはインドのなかでも飲酒にはとくに手厳しい州だ。まず第一、どこにも売ってない。この土地では酒の空きビンさえみつけることは至難である。
同じくグジャラートにあるバブナガルという町のホテルで、ベジタリアンターリーを食べながらその話をしてみたら、宿泊客のオヤジが「アラビア海にポツッと浮かぶディーウ島にいけば酒が安く飲めるよ」と教えてくれた。
グジャラート州は昔から白衣派(シヴェタンバル)のホームグラウンドとして知られている。五世紀にはバラビーの聖典結集、一二世紀にはヘーマチャンドラというやり手の僧が活躍し、国家規模でジャインダルマを徹底させた。中村元はいう。
かつてグジャラートの王クマーラパーラは、ヘーマチャンドラの感化を受けてジャイナ教を信奉し、その結果、王みずから肉食と狩猟を断ったのみならず、国内に令して一般に屠殺・肉食・飲酒・賭博を禁じた。この禁令は厳重に励行されたので、グジャラートはジャイナの模範と仰がれるようになり、屠殺業者は職業を失った変わりに三年間の収入をもって弁償され、バラモンは犠牲獣を屠らずして、穀物の供物を神に捧げるようになったという
十二世紀にヘーマチャンドラがこの地を教化していらい、グジャラートでは禁酒、菜食が徹底的に守られてきた。しかし、土地の民がそれを苦にしているようにもみえない。インド一般の食生活は、もとから青虫みたいなもんなのだ。しかも野菜とマサラだけで、万華鏡のように多彩な味わいをつくりだす。グジャラートのヴェジタリアンターリーは、お世辞ぬきにインド一うまかった。
グジャラートが州規模でヴェジタリアニズムを守っているのは、なにもジャイナだけのせいではない。ここはヒンドゥー教の一派である「ヴァイシュナヴァ派」の土地でもある。ヴィシュヌ神への熱烈な信愛と衆生一切の解脱を説くこの宗派は、ジャイナとおなじく清貧と粗食を重んじることから、この地で両宗はたがいに習合しあっている。
ガンディーの母プリータバーイはとくに敬虔なヴァイシュナヴァの信徒だったらしく、しばしば長い断食を宣言しては、幼いガンディーをはらはらさせたという。面白いのは、ガンディーがイギリス留学する際、この母親は「肉と酒と女に触れないこと」を自分が信頼するジャイナ僧の前で彼に誓わせたという話だ。この逸話からも、ガンディーはグジャラート精神の体現者だということに気づくであろう。
こうしてみると、グジャラート州がいまだに野生動物の宝庫であるというのも納得のいく話である。ジャイナの聖地ギルナールから三十キロほどのところにあるギルの森には、アジア最後のライオンが生息している。この土地だけにライオンが生き残ったというのは、たんなる自然環境の偶然ではない。
グジャラートで生活する民の多くは、家畜の水牛がおそわれたり、家族が殺されても、その報復としてライオンを殺したりはしない。それどころかライオンの獲物となる動物にも手出しをしないのだという。ジャイナとヴァイシュナヴァが重んじる「不殺生(アヒンサー)」の原理を、彼らは昔から忠実に守っているのである。(2003.08.23記)
49.前世を記憶するジャイナたち
ぼくはラクハンではない。ジャイナ様と呼びなさい。ぼくはH・L・ジャイナだ
インドの転生例を記録した、サトワント・パスリチャ教授の著書「生まれ変わりの研究」には、ジャイナが実際に転生したというサンプルが紹介されている。このラクハンという子供は四才半のころ、自分のことを突然H・L・ジャイナと名のり、前世の記憶を語りだした。
ラクハンは、変わった行動特徴をいくつか示した。一日の最後の食事を日没前にとり、漉過した水を飲みたがったのである。昆虫に対するラクハンの態度も、家族のものや村の同年齢の少年たちとは異なっており、それを殺すことはなかった。これらは敬虔なジャイナ教徒の特徴なのである。
調査の結果、このH・L・ジャイナという人物は実在し、しかもかなり有名人だったことがわかった。彼は病院で亡くなったのだが、その死亡日時は、ラクハンの誕生日のちょうど九ヶ月前だった。パスリチャ教授は、このラクハンの他にもシャルマというジャイナの転生例を報告している。この子の場合も、生まれ変わるまでの期間は九ヶ月で、ラクハンの事例とぴったり一致した。
この分野の権威、イアン・スティーブンソン博士の「前世を記憶する子供達」にも、ジャイナの転生サンプルが公開されている。
ジャイナ教徒の考え方と一致するのは、ラジュル・シャーの事例である。また、この事例の前世の人格は、ラジュルの家族が確信をもってジャイナ教の「公式」を採用したおかげでつきとめられたのであった。
ラジュルはギータという前世の人格の名前と、そのころ住んでいたジュナガドゥという町の名前をあげた。そこでラジュルの家族は、代表をひとりジュナガドゥに派遣した。その家族は、その町で、ラジュルが生まれる九ヶ月前の住民死亡台帳を調べた。するとその月に、ギータという人物の名前をみつけ、その父親をさがしあてた。ラジュルの家族はそうして、前世についてラジュルが語ったほかの事柄も事実であることを確認したのである
死の瞬間、霊魂はすぐさま来世の肉体となる受精卵にむすびつく。だから生まれ変わるまでの期間は、人間だとちょうど妊娠期間にあたる九ケ月をみればよい。これがジャイナのいう「公式」だ。パスリチャ教授とスティーブンソン博士が調査した全サンプルが、なんとこの公式に一致したのである。
転生さわぎといえば、日本でも江戸時代末期、国学者の平田篤胤が調査した「勝五郎事件」が知られており、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)によって海外にも紹介されたことがある。勝五郎は七才のとき、疱瘡で死んだ勝蔵という前世の記憶を語りだし、それが事実と証明された。勝五郎が転生したのは、勝蔵の死から三年後だったらしい。このケースではジャイナの公式と違い、かなりのミッシングリンクがある。
自身の神秘体験をもとに、女優シャーリー・マクレーンが輪廻転生の記憶をつづった著書「アウト・オン・ア・リム」が、全米ミリオンセラーになったときく。「人は役者、人生は舞台」とはシェイクスピアだが、いまや輪廻転生は、人生の劇場化にかかせない舞台装置となりつつある。あるいは、ただの転身願望か。(2003.08.21記)
48.カルマという物質
インドから帰国後すぐ、テレビで「治癒と心」という番組を見た。
ビル・モイヤーズというアメリカきっての名ジャーナリストの案内により、医療の現場や、東洋医学を紹介していくすぐれたプログラムで、なかでも印象に残ったのは第二回目の「感情と免疫系」だった。
病は気から、とはよくきくセリフだが、それは単なる俗信ではない。心持ちや情感といった人間の精神活動は、じつは特定の物質がかかわっているのだとマーガレット・ケメニー心理学博士は説明する。それは「ニューロペプチド」と呼ばれ、免疫系や神経系というネットワークを中心とした、精神と物質の対称性が解明されつつある、という内容だった。
著名なSF作家であるフィリップ・K・ディックの作品に、「アンドロイドは電気羊の夢を見るか?」という近未来小説がある。冒頭に「ムードオルガン」という感情調節マシーンが登場するのだが、これはダイヤルを選択するだけで「自虐的抑鬱」とか、「恍惚の性的歓喜」とか、お好みで感情をデザインできる装置なのだ。主人公のリックと妻のイーガンは、のっけからどのムードにダイヤルするかで悶着してしまう。
ここまで便利にはいかないが、我々は「酒」とか、「麻薬」というムードオルガンをすでに所有している。これらは人類最古のオルガンといえるであろう。現代にいたっては、アドレナリン、アンフェタミンと、まだまだ鍵盤の数はふえつつある。「感情は物理現象だ」といっても、誰も驚かない時代になった。
人智学者として知られるルドルフ・シュタイナーは、二十世紀を評して「人間の精神力が物質に集中している時代」と語った。今日の資本主義は、この時代精神が物質化し、ふくれあがったマス・モンスターなのかもしれない。
じつは二五○○年前、すでに感情を物質視していたのが、他でもないマハーヴィーラであった。ジャイナのニューロペプチドは、「カルマ」とよばれている。楽しい、苦しい、快いといった諸感情は、すべて霊魂にとりついたカルマによる現象であり、輪廻の原因もその物質のせいだと彼は語る。
かように大胆な理論をブチかましたのは、後にも先にもインドでも、いや世界でもマハーヴィーラしかいないのではないか。ジャイナ独自の輪廻モデルは、このような切り口から誕生したのである。(2003.08.20記)
47.霊魂その3
ジャイナが「自己」という場合、それは肉体に宿る霊魂のことを示している。真の自己とは、霊魂という内的自己だ。肉体なんていうものは、霊魂の乗りもの、いわばレンタカーくらいにしか彼らは考えていない。人間の体細胞は、一年で九八パーセントが入れ換わるというから、この発想はまんざらウソともいえない。無常なる肉体の重心に不滅の霊魂をおく。考えてみれば昔ながらのオーソドックスな霊魂観をジャイナは採用しているわけである。
霊魂があるか、ないか、といった議論は現代でも珍しくないが、古代インドでもかなりの悶着があったらしい。一方にはヴェーダーンタやジャイナなどの霊魂派、もう一方には唯物論、仏教といった霊魂否定派がそれぞれ陣をはっている。
このなかでヴェーダーンタは、アートマンという霊魂観をもつことで知られている。アートマン(我)とは、全宇宙であるブラフマン(梵)のホログラムみたいなものであり、もともと我と梵はひとつであるという。これは不二一元論とか、帰一思想とか呼ばれている。
だから真の自我というものは、宇宙に一者しかない。自分とか他人とかを区別する自我なんていうものは、真の自我ではない。それは幻覚だ。心というビデオが写しだす、架空の映像にすぎない。幻覚に生きた人は死んでも幻覚に悩まされ、ふたたび輪廻にとらわれてしまう。 欲望という心の電源をオフにして幻の映像を消しさったとき、はじめてブラフマンという真の映像がみずからの画面にたちあらわれる。そしてアートマンは、自他をこえた不滅の実在とひとつになるという。これが「梵我一如」の境地である。ヴェーダーンタにとって「わたしはアートマンであり、ブラフマンである」わけだ。
それが仏教になると、霊魂だけでなくいかなる実在も幻想だというのだから過激である。無我の思想など、その代名詞といえるかもしれない。彼らはこう語る―ブラフマンのように、永遠不滅のものなどひとつもない。さらにアートマンをすえるなど、ウサギに角があるといってるようなものだ―と。「仏教徒は仮面をかぶった唯物論者である」などと評するものもいたというが、このセリフは当たらずとも遠からずだと思う。
仏教徒は、自我という「働き」は認める。しかし、その影に「働き手」を認めない。テレビにネコが写っているからといって、裏蓋をあけたらネコがでてくるか。同じように肉体の裏蓋をはずしたら、霊魂が出てくるというのか。「自分」とは、因果という軸にそってたえず変化する、現象としての「自分」である。それだけのことだし、それで充分だ。今の自分は昨日の自分ではない。仏教徒にとって確かに「自分はいない」のである。
ルーマニアの思想家シオランはいう。
仏教とはまた、なんという奇妙な宗教であろうか。いたるところに苦を見ながら、同時に、その苦を、非現実のものだと公言するのだから
仏教徒のいうように無我をすえると、輪廻したり解脱したりするのはいったい何なのか、その主体が説明しづらい。ニルヴァナの境地も無常だというのか?
そこらへんジャイナは霊魂の存在を疑わないので、輪廻するのも解脱するのも霊魂なんです、といえばそれですむ。こうしてみると、インドで生まれた宗教のなかでも、ジャイナはもっともシンプルな解脱モデルを設定しているともいえよう。仏教における輪廻の主体を説明しろ、なんてせまられたら考えるまえに逃げだしたくなる。(2003.08.18記)
46.ダルマのページ
これまでの怠慢を詫びつつ、やっとダルマのページに着手開始。まずはPDFで配布していた解説をちゃんとブラウザで読めるようにしていきます。わが国で出版されているジャイナ関連の書物はみな学者による学者のためのものばかりでシロウトには厳しいから、とっかかりには最適のはず。とうぶん文字のみですがご勘弁ください。おいおい図版やリンクを追加していきます。せっかくの誕生日もジャイナの更新作業でおしまいかよ...しかも終日雨。マスタァっ! 強いおサケちょうだいっ!(2003.08.14記)
45.「私はアヒンサーの百戦練磨の兵士である」
動物を殺すのはかわいそうだとか、そんなセンチメンタルな気持ちからアヒンサーを叫ぶわけではない。感傷など自己欺瞞にすぎない。それは哀れみとも違う。アヒンサーは感情を伴わない。必要なのは霊的意志なのだ。魂の問題をどこまでも究明し、精神をどこまでも鋭利化させたその頂点から、アヒンサーが流れ出すのである。
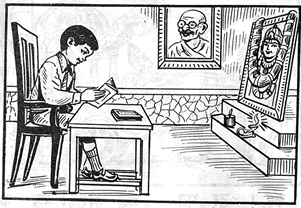
世界と自分との関係に意識的になること。そのための闘争がアヒンサーだ。だから、社会のありとあらゆる場面でアヒンサーが立ち上がるのを理解できるだろう。それをインド独立という命題に応用したのが、かのガンディーなのである。
アヒンサーが行動主義に結びつくと、それはラディカルで、ときには帝国主義にも屈せぬ「愛の武器」になる。それをガンディーは「サティヤーグラハ」という造語で表現した。「真理の実践」という意味である。
しかし俗世を離れた個人だけが救済を約束されるジャイナの解放論に、ガンディーはどうしても同意できず、アヒンサーを全人類の救済原理にまで高めることを生涯の仕事とした。「すべての人の目から涙を拭い去ること」ができるまで、天国には行きたくないと彼は考えたのである。ガンディーは、ジャイナを大乗化したといえないであろうか。(2003.08.11記)
44.ジャイナ vs. クリスチャンその2
婦長さんの語ったヘビ騒動の逸話は、考えるとけっこう根が深い。つまり、自分を害しようという動物を殺すか、それともそのまま自分が害されるにまかせるか、どっちを選択するかというジャイナにとっては踏み絵的な問題を含んでいるのである。実は、ガンディーがまだ若いころ、ジャイナの在俗信者ラーイチャンドバーイと交わした往復書簡のなかにも似たような話がでてくる。
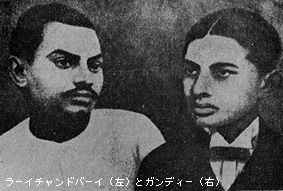
ガンディーがジャイナの哲理から多大な影響を受けていたことは、もっと強調されてしかるべきであろう。ロマン・ロランはその著書「マハトマ・ガンディー」のなかで、「彼の両親はジャイナ教に帰依していたと錯覚されるほど、一家は不殺生、無所有といった、ジャイナ教の感化を大きく受けていた」と書き記している。またガンディーの母プリータバーイは、信頼していたジャイナ僧の前で、「酒、女、肉に触れぬこと」を彼に誓わせ、やっと英国留学を認めたという逸話もある。
このように少年時代からジャイナに接する機会が多かったガンディーだが、それが決定的となったのが、ラーイチャンドバーイとの出会いであった。「ガンディー」の著者である森本達雄氏はいう。
ガンディーは彼を一目見たときから、その豊かな学識と高潔な人格に心をひかれ、その人のうちに、純粋な真理の探究者の生きた実例を見たのである。そして彼は、ラーイチャンドバーイとの交友をとおして―教儀や儀式によらず―ジャイナ教の思想体系を、とくにその中心思想であるアヒンサーの哲理を学ぶことができた。すなわち、彼はアヒンサーを、ただ機械的に暴力を避けるという消極的な善行ではなく、人類にとどまらず、生きとし生けるものいっさいのものとの生命の連帯感を認識することから生まれる積極的・普遍的な愛の行として受けとめたのである....
そしてラーイチャンドバーイが31歳の若さで他界するまで、二人の親交は変わることがなかった。後年ガンディーは、トルストイ、ラースキン、そしてラーイチャンドバーイを「わたしの生涯に大きな影響を与えた三人の現代人」と呼んでいる。
ガンディー:ヘビがぼくに噛みつこうとしているとして、それを噛むにまかせておくべきだろうか。それとも自分の命を救う唯一の手段として、それを殺すべきだろうか。
ラーイチャンドバーイ:ヘビが噛むのに任せておけ、という人はおそらくいまい。しかしぼくはあえて、それが正道だといっておきたい。肉体など脆いもので、魂にのしかかる大変なお荷物だと君が気づいていればの話だが。つまり徳を望む者なら、そんな状況では自分の肉などヘビにくれてやるのがいい。しかし徳を望まぬものは、どうやりすごせばいいだろう? ぼくが言えることは、どうして彼らに地獄へ行ってくれなんて言えるかということだ。つまり、ヘビを殺しちまえと。内面の磨きが足りない人なら、彼らに殺せと助言するかもしれない。しかし、ぼくも君も、そんな愚行をする人間じゃないはずだ。
ラーイチャンドバーイは、この手紙で明らかに肉体に対する霊の至上を説いている。それを「肉は脆いものである」というイエスの言葉に置きかえるなら、ジャイナとクリスチャンは、決して理想を異にしていない。ぼくが婦長に反論する理由など、実は何もないのだ。(2003.08.10記)
43.ジャイナ vs. クリスチャン
カルナータカ州の都バンガロールは作者の大好きな街である。しかし旅行者の評判はあまりよくない。なぜなら、ここはあんまりキレイすぎて、涼しすぎて、インドらしい面白さがないというのである。たしかに一理あるのだが、口元に気さくな笑みを含ませ、しかも紳士的なこの街の住人たちはとても魅力的だった。「カルナータカの微笑」はこんな大都会にあっても健在なのである。
しかし食い物にはひどい目にあった。ファーストフード屋で食ったコロッケバーガーが大当たりしたのである。いきなり冷や汗がふきだし、目の前は真っ暗になった。これはただの腹痛じゃないと判断するや、オートリクシャーをつかまえ、「どこでもいいから開いてる病院へ!」と叫んだ。その日は運悪く日曜日だったのだ。
近所の個人病院についたとたん、ぼくは洗面台一杯に嘔吐すると同時に、下のほうも暴発してしまった。上も下も、もう自分の意志ではどうにもならない。「人間は一本の管である」という稲垣足穂の言葉を体感した一瞬であった。本人はもう死ぬ思いだったが、単に「日曜日だから」という理由で、誰も診てくれない。
診察してくれる病院をやっと捜しあてたとたん、即入院と決まり、尻に注射二本ぶちこまれ、点滴までされてしまった。あーあ、なんだかオオゲサになっちゃったなー、なんて思ってるうちに、薬が効いてきたのか、とにかく眠くてしょうがない。日本人は珍しいらしく、院長から婦長から、ねほりはほり質問の矢を浴びせてくる。病院のくせに、寝させてくれないのだ。しょうがないのでジャイナの勉強にきたこと、アヒンサーのこと、ヴェジタリアニズムのことなどを朦朧としたまま話していた。すると婦長がいくぶんキツイ口調でこう言い返した。
「もちろん私は何の肉でも食べます。聖書を読んでごらんなさい。あらゆる自然環境は、人間が利用するために神が創造したと書いてあるじゃないですか」
彼女はクリスチャンだったのだ。
「でも動物だって人間に殺されたくはないでしょう。痛みを感じているでしょう」
「でも動物だって人間を殺すでしょう? こないだ、隣のジャイナ教徒の家に、大きなヘビがまぎれこんだけど、彼らは戒律があるから当然ヘビを殺せない。部屋から追い払ったのはいいけど、よりによって私の家に追い出すとはね。結局始末したのはこの私なのよ。ジャイナ教徒は、そういう損な役回りを他教徒に押しつけているだけね」
「ちょっと寝させてくださいよ」
「どうやらその議論は避けたいようね。あなたは一度マハーヴィーラでなく、ジーザスの研究をしてみるといいでしょう」
しかし、聖書にイエスが肉食したというくだりは一切ない。旧約聖書においても、ダニエルは「穀物と水」だけで神の子となり、エゼキエルもエホバにこう証しをしている。
わたしは若い時から今に至るまで、死体となったものも、引き裂かれた動物も食べたことはありません。わたしの口にいとわしい肉が入ったこともありません
むしろクリスチャンこそ、ヴェジタリアンになるべきなのだ。マニ教、コプト教、カタリ派など、異端とよばれた宗派のほうが、その点では聖書により忠実だった...(続く)(2003.08.09記)
42.無題
この世の名誉、栄光のたぐいはすべて、追いかければ追いかけるほど遠ざかる自分の影のようなものです。それにそっぽをおむきなさい。ひとたびあなたが太陽にむかって進みだせば、今度は影のほうからイヤでもあなたについてくるでしょう。
アマル・ムニ・マハラジ著 『アマル・ヴァニ』P65
41.苦行は苦しくない(40より続く)
十二年ものあいだ、寝るときも、歩くときも、いつでも右手をあげたままだという、ある苦行者の記事を読んだことがある。
そのサドゥーいわく、「自分のためにやってるわけじゃないから、苦しくないよ」とのこと。こんなリクツもあるんだな、と妙に関心するとともに、そのおどけた様子がとてもユーモラスに映ったのを記憶している。
ジャイナもそうだが、インドの苦行者たちには、ぼくらのイメージする悲痛さがまるでない。それどころかムチャクチャに明るい。どうも彼らは苦行を楽しんでいるフシがある。
このサドゥーが語ったように、自己放棄をした人間は苦しまない。苦行者は苦しくない。マハーヴィーラは口元にいつも微笑をたたえていた。「私は修行を楽しんでいるのです」とガンディーは語った。ブッダが苦楽を遠ざけるなら、マハーヴィーラは苦とひとつになる。時そのものには、時が流れていないように。エックハルトは言う。
神の恩寵を受持する魂にとってすべてのものを放下することはまことに容易なことであって、如何なる人にとってもそれ以上に容易なことはなかったほどである。いや、私は更に言いたい。神の恩寵を受持する魂にとってすべてのものを放下することはまことに楽しいことであって、如何なる人にとってもそれ以上に楽しいことはなかったほどである。
「恩寵について」上田閑照著『エックハルト』より p459 講談社学術文庫
自己放棄とは、刹那に自殺しつづけるということである。炎はみずからを焼きつくし、不断に生成消滅をくりかえすことで、つねにフレッシュな光をはなつ。それに着想をえたヘラクレイトスは、「万物は火である」と語った。諸行無常なんかも、おなじく万物が「空」から不断に開示するピチピチ感を説いたものであって、決してニヒリズムではない。
自己放棄を楽しむとき、人間は真の生を生きはじめる。これはマハーヴィーラやブッダに先んじて、クリシュナが「バガヴァット・ギーター」のなかですでに説いていたヨガの黄金律だ。ジャイナや仏教はそれをリファインしたにすぎないのではないか。(2003.08.06記)
40.自然に帰るな(39より続く)
人間だけが時間のなかに生きている。人間だけが時間に引き裂かれている。
時間の呪縛からのがれるために、ここはひとつ動物のように野生にもどり、「時を忘れる」のも一手ではないだろうか。「自然に帰れ」というわけである。
しかし「自然に帰る」ことは、暴力と競争のダルマにしたがうことである。いっけん平和そうな植物の世界でさえ、企業競争にもひとしい「日照権」ゲームが繰り広げられている。弱肉強食を法とする動物の世界など、そのものといっていいだろう。 世界にあまたある神話のほとんども、「殺す、食べる、産む」のジャンケンでつくられている。人間がもつ「暴力、肉食、生殖」の野生が、神話の世界ではメタファーの星座となって輝いているのである。
このような「暴力と競争」こそ素晴らしい生きかただと信じる人は、野生に徹してみてはどうだろう。インドで発見されたオオカミ少女のように、遺伝子にセットされた野生のプログラムをおもいっきり開放すればいい。
しかしマハーヴィーラは、そんな人間の深層にかがやく星座たちを、アヒンサーというこん棒でかき乱そうとする。彼は逆に、「非暴力、非肉食、非生殖」の法(のり)に生きることこそ人間の気高さであり、人間たる証しだと考えた。「自然に帰るな」というのである。じゃあどうやって時間の二枚刃から逃れたらいいのか。それは「時そのもの」になることだ。時間に流されないのは、時間そのものしかないからである。
南インドに広くみられる「踊るシヴァ」の神像は、片手に時をきざむカスタネットを、もう一方にそれを焼きつくす炎を手にしている。シヴァは時間の神カーラを殺すことで、時間そのものになり、時間の生みだす創造と破壊、つまり生と死のサイクルをつかさどる神となった。だからシヴァ神のダンスには、時間をのりこえるための叡智がかくされている。つまり「時そのもの」になるには、「時を殺す」しかないと。
ギリシア神話にも、時間の神クロノスを殺したゼウスという、シヴァと共通のイメージを見出だすことができる。ゼウスも時間を殺すことで、最高神の座を手にしたのである。クロノスはギリシア文字の「Χ(ch)」ではじまるが、これは時間の二枚刃が自我を切り裂く十字架的なイメージに通じている。ジャイナの経典「アーヤーランガ」のなかに、こんな一説がある。
カルマの堆積のうちに住んでいるものは、死神(カーラ)にとらわれている。かれらは繰り返し輪廻の生におもむく
この「死神」を「時間」と読んだらどうだろう。つまり輪廻とは「時にとらわれている」ことであると。
ジャイナの教えによると、カルマが霊魂を呪縛する時間は、その行為にたいする欲の強さに比例する。つまり欲を滅することができれば、カルマが支配する「有限の時」は消えていくのである。これがジャイナ流の「時殺」戦略だ。「アカーラ・ヨガ」とでも命名しようか。
アカーラ・ヨガに生きるとき、ぼくたちは無限にして無である「時そのもの」に生きることができる。道元のいうように、「生は時なり。仏も時なり」なのだから。ヴィトゲンシュタインもこう語っている。(2003.08.05記)
ところで、死は生の出来事ではない。人は死を体験することはできない。もしも、永遠とは限りない時間持続ではなしに無時間性のことである、と考えるなら、現在のうちに生きている人は、永遠に生きていることになる。われらの生に終りはない。われらの視野に限りがないのと同じように
39.時間の二枚刃
人間はふたつの時間系に生きている。
ひとつは、始めもなく、終りもない、無限につづく時間系だ。この裏をかえして、時間は無いといったらどうであろう。実はどちらも同じことなのである。たとえば、円を無限に大きくしていくと、円の曲率は無限に小さくなり、ついには直線になってしまうように。つまり円が「無限に大きい」ということは、円で「無い」のと同一なのである。
このように「無限の世界」においては、無限が無に、曲線が直線に等しくなるといった「矛盾の一致」がおこる。「トマス福音書」でイエスも弟子たちにこう説き明かす。
あなたがたが二を一にし、内を外に、外を内に、上を下にするとき、あなたがたは神の御国にはいるであろう(二二)
おなじように、時間が無限であれ、無であれ、サイクリックであれリニアーであれ、無限の世界ではどっちだってかまわない。そもそも直線は無限だから直線なのであって、かぎりがあったらそりゃ「線分」だ。ユダヤ・キリストの終末思想は、直線的というより、線分的といったほうがいい。
アダムとイブの神話にみるように、人間は他の動物とはちがい、自分がいつか死ぬ身であるのを「知って」いる。過去にさかのぼれば「生」という始点があり、未来には「死」という終点がまっている。人はみずからの死を自覚した瞬間から、「無限の時」のほかにもうひとつ、「有限の時」を生きることになった。これは因果関係、つまりカルマが支配する時間系だ。「人生の鋸」と題した断章で、アマル・ムニジーはいう。
息を吸って、息を吐く。この動作はたえまなく何十年とつづきます。しかし人々は、これがいったい何を意味しているのか気にすることはありません。実をいうと、これは人生の喉をかき切る鋸の音なのです。息することは生の証しなり、とみな信じているようですが、私には刻々と死を告げる時計の音にしか聞こえません
これら二つの時間系は、ひとつだけ交点をもつ。それは「いま、ここ」にいる「わたし」である。逆からみると、「わたし」は二枚刃をもつ時間のカミソリによって、無限と有限に切り裂かれ、かろうじて喉笛だけ残してつながっているということだ。
みずからがまっぷたつに切り裂かれる恐怖から、「わたし」はなんとかこの裂け目を繕おうとするのだが、そう思考する「わたし」がいるかぎり、時間は切り裂くのをやめない。なぜならその「裂け目」は「わたし」の思考がつくったものだからだ。つまり裂くのも、裂かれるのも「わたし」であり、それを繕うのも「わたし」というぐあいに、思考は無限循環に陥ってしまうのである。この自己矛盾は、人間だけの苦悩であり、かつ人間の証しでもあるのだ。
股下には闇につつまれた深い渓谷がひろがり、その奥底には、時間のどす黒いうねりが横たわっている。人が人であるかぎりは、その渓谷をまたぎ両崖に足場をおくしかない。そんなリアルな恐怖を体感させるのが、二元論のねらいなのである。
渓谷をまたいだままの「不自由な安定」に甘んじるよりは、いさぎよく谷底にジャンプするという「不安定な自由」をえらぶ。二元論とは、そのような選択をこそ鼓舞する思想なのだ。自由のためなら、どんなリスクも逃げずに受けとめる。だから人生が劇場化するのである。(2003.08.04記)
38.シャドウ・ヒストリー
ブッダガヤーのマハーボディ・テンプルを訪れとき、不思議に思ったことがあった。寺院が周囲よりも一段低い場所に建っているのである。およそ寺院らしくないレイアウトではないか。
「あれはムスリムの破壊から寺院を守ろうとして、当時の民衆が寺院を埋めた名残なんですね。しかも守ったのは仏教徒じゃなくて、ヒンドゥー教徒だったんです。仏教もヒンドゥー教なんだから、と彼らは考えていたんでしょう」
ガヤーの日本寺で駐在僧の小林さんからこの話をきいたとき、インドのインドらしさにあらためて触れた気がした。
「ジャイナはヒンドゥー教だよ」という声をインドではよく耳にする。そのたびに「ちがうよ、ジャイナはジャイナさ」となかばムキになって反論したものだった。しかし今になって考えると、ジャイナがヒンドゥー教で「ある」のではなく、そう「しておく」ことで、彼らはマイノリティであるジャイン・コミュニティと大過なくやってきたのだ。それは仏教についても同じだったのではないか。
亡命したダライラマを受入れ、チベット仏教を救ったインド。ムスリムの迫害から逃れてきたゾロアスター教徒を迎えいれたインド。インドというところは、宗教の孤児たちをわが子のように迎えてくれる、やさしいお母さんのような土地なのである。「ヒンド・スワラージ」のなかで、ガンディーはこう語っている。
もし歴史が王や皇帝たちの行跡を意味するなら、そのような歴史に、魂の力、すなわち受動的抵抗の証拠などあろうはずはありません。鈴の鉱山から銀の鉱石が採れるわけはありません。世間で知られている歴史というのは、世界の戦争の記録のことです。ですからイギリス人のあいだには、歴史をもたない民族―すなわち、戦争を知らない民族―は幸いである、という諺があります。王たちがどうしたとか、どんなふうにして互いに敵同士になったとか、殺し合ったとかいうようなことが、詳細に歴史に記録されています。が、もしこれが世界で起こったことのすべてであるというのなら、世界はとっくのむかしに終りを告げていたことでしょう。世界の物語が戦争とともに始まっていたのなら、いまごろは、生きている人間など一人として見られなかったことでしょう。
この世界にこれだけ多くの人間がいまも生きているという事実こそは、世界が武力にではなく、真理すなわち愛の力にもとづいているということを示すものです。ですから、この力の勝利の最大にして、もっとも申し分のない証拠は、世界に戦争が繰り返されたにもかかわらず、世界がいまなお存続しているという事実のうちに見出だされます
インドの歴史には、つねに魂の力がシャドウ・ヒストリーとなって底流している。裏インド史の一ページに、ぜひ「マハーボディテンプルを守ったヒンドゥーたち」を加えておきたい。そして、ジャイナがいまなお生き抜いているという奇跡も。よくジャイナは歴史や発展にとぼしいといわれるが、それは彼らがコミュナル・トラブルを起こすことがまったくなかったからだ。やられたら、やられっぱなしだった。それでも生き残った。それがジャイナであり、インドなのである。(2003.08.03記)
37.無題
腋臭(わきが)のある人間に君は腹を立てるのか。息のくさい人間に腹を立てるのか。その人間がどうしたらいいというのだ。彼はそういう口を持っているのだ、またそういう脇をもっているのだ。そういうものからそういうものが発散するのは止むをえないことではないか。
マルクス・アウレーリウス『自省録』
(2003.07.31記)
36.獺(かわうそ)
会社を辞めて自宅で仕事をしていることもあり、ちかごろ近所の飲み屋にくわしくなった。仕事が煮詰まってどうしようもなくなった深夜、ひとり自転車で小田急線沿いを徘徊する。
今日たずねたお店の名前は『獺(かわうそ)』という。名前からしてちょっとよいではないか。しかも店内にはいっただけで「当たり!」とおもわずもらしたくなるたたづまいである。
カウンターには流木をさりげなくあしらっており、それを照らすハンドメイドの照明器具には、ほおづきをかぶせてある。葉脈が透かしだされてなんともやさしい明かりだ。
ざる豆腐、みょうがとオクラの酢の物、長芋の黒胡椒焼き、豚肉の柚胡椒など、どれもシンプルながら素材自体のうまみが堪能できるできばえであり、ますます当たり感をつよめる。
酒はマッコリをいただく。発泡しているので3分ほど待ってほしいという。スパークリングワインのような舌ざわりであった。
ところで気になる店名の由来であるが、
川魚が大好きなカワウソには、捕らえた魚を、いきなりではなく、石の上にたくさん並べ立ててから食する習性があるといわれています。その様子を「獺祭(だっさい)」と呼ぶのですが、そんな仕草が「かわいいな」と....
すっかり夢見心地となり、店を出たあともそのまま自転車で徘徊した。24時間営業の温泉にたどりついたが、1800円という値段にびびってそのまま帰宅した。(2003.07.11記)
35.「自」の宗教
あなたを救うのは、あなた自身しかいない
これがジャイナの救済原理のすべてである。クリシュナムルティもまた曰く、
皆さんを救うことができる、いかなる経典もなく、いかなる指導者もない。皆さんは、一人の人間として、完全に自分自身の足で立たなければならないという戦慄すべき事実、恐るべき事実を悟らねばなりません
ジャイナは「自」の宗教だ。自発、自力、自律、そして自由。自己啓示にはじまり、自己神化するプロセスこそ、ジャイナ道にほかならない。ジナとはもともと「己に勝利したもの」の意味である。白衣派スターナカヴァーシのアマル・ムニジーもこう語っている。
あなたは運命の女神をお探しでしょうか。どっかの誰かや、どっかの権威ならあなたの運命を決めることができるとでもお思いでしょうか。人生の書物を、誰かほかの人に書き直してもらうおつもりですか。みずからの足ですっくと立ち、歩み続けるものだけが、みずからの運命をみいだすことができるのです。あなたが望むなら、あなたは望んだとおりのものになる。天国と地獄はひとしくあなたの内にあります
このようなジャイナの自力主義は、みずからの死さえも、みずからの意志において行おうとする「自殺行」の慣習に象徴されている。ここには、出産や死といった自然現象に対する、知性の反逆がある。カルマの作品たる肉体におぼれないための、グノーシスな意志が見えるのである。
だから神による自動的な救済システムなど、ジャイナにはかけらも無い。大乗仏教の「廻向」のように、ボサツさまが果報を譲ってくれることもない。世界宗教は、たいてい受動的救済をベースとして発展してきた。あくまで孤独を基調とするジャイナやマニ教のような思想は、消えゆく運命にあるのかもしれない。栗本慎一郎氏はいう。
日本人は、ジャイナ教の存在などにほとんど触れたことはあるまい。(中略)主体的な宗教は、近代社会では力をもたないからである。なぜなら、近代社会は個々人の自立をうたうが、実際にはその個々人が明確には自立していないことが成立の前提になるのであった『幻想としての文明』
すべての因縁を個人に帰するジャイナの救済論に、たいていの日本人は辟易するであろう。神というおせっかい屋の介入は、支配を望む人々には往々にして居心地がいいのである。
しかしその一方で、ジャイナほど楽観的な宗教がほかにあるだろうか。運命さえ、自力でどうにでも料理できると力強く語るのだから。自力救済の思想とは、自由という元素をただひたすら結晶化したものなのだ。(2003.06.09記)
34.独立しました
サーバーだけでなく本人も独立。ただいま屋号募集中なのである。
それはさておき、この日記で紹介した仲御徒町のジャイナ礼拝堂の場所をおしえてほしい、という人がけっこうおりました。本当はこのページに地図でものせればラクなのだけれど、マスメディアに知れるのはやっかいなので、やはりこっそり教えるという形で今後もやってこうと思います。
途中、立ち食いの讃岐うどんのお店があるが、ここは安くて旨い。ざるうどんがオススメ。ジャイナもいたりするかも。(2003.06.05記)
33.というわけで
会社辞めます。(2003.04.21記)
32.独立はいいもんだ
J-COMのわび住まいから解放され、当サイトも念願の独立である(レンタルだけど)。これまでは容量ギリギリのところで日記のみシコシコ更新してきたわけだが、今後は写真なんかアップしちゃったりできる。回線も速くなったので動画もできる。でも悲しいかな、仕事が忙しい。こっちも独立するしかないか?(2003.03.16記)
31.時間とお金
イエスが生きていたイスラエルでも、「時は金なり」が人の心にしみわたっていたのだろうか。マタイ福音書をみると、彼はそんなフランクリン的思考をブチ壊そうとしていたのがみてとれる。
天の王国は、自分のぶどう園に働き人を雇うため朝早く出かけた人、そんな家あるじのようだからです(二十・一)
この「ぶどう園の家あるじ」は、一日一デナリの賃金という約束で朝から働いていた「最初の者」と、夕から一時間だけしか働いてない「最後の者」にも、おなじ一デナリの賃金を支払うのである。それは不当なあつかいだと抗議する「最初の者」にたいして、彼はこういう。
君、わたしはあなたに何も不当なことはしていない。あなたはわたしと一デナリで合意したではないか。あなたの分を受けとって行きなさい。わたしは“この最後の者にも”あなたと同じように与えたいのだ。わたしが自分のもので自分の望むことを行ってよいではないか。それとも、わたしが善良なので、あなたの目はよこしまになるのか
人よりちょっと「よこしま」なものが、ちょっとだけ富を増やしていく。人よりちょっとだけ広く耕したものが、ちょっとだけ多く収穫をえるように。ちょっとだけ長く働いたものが、ちょっとだけ多めに賃金を受けとるように。
それが幾世代もつづくと、「ヨコシマさん」には資産というものができる。その成り上がりどもは、「長」や「王」という名で「最後の者」を蔑み、家畜のようにこき使う。時の差は富の差を生み、やがて力の差を生みだすのである。
資産からはまず「所有」の観念が生まれる。つぎにその所有者を「殺す」もの、「盗む」もの、その盗みを「偽る」もの、その偽りを「裁く」もの、といったぐあいに、あとは尻取りみたいに「よこしま」が感染し、さまざまな悪徳がウジャウジャわきでてくる。これらはすべて「時の差」というパンドラの箱から出てきたものだ。それにしっかりフタをするのが「家あるじ」であり、天の王国なのである。最後にイエスは次のような「矛盾の一致」でしめくくる。
このように、最初のものが最後に、最後のものが最初になるでしょう
これを経済学の法にすえ、貧富のない社会を築こうとしたのがラースキンだ。彼の著書「この最後の者にも」は、当時の経済学者や一般大衆からもうさんざんにコキおろされたが、ガンディーは自給自足の共同農場「フェニックス農園」をひらき、その実践をもってラースキンにエールを送った。
自給自足というライフスタイルは、自分が労働者であり、経営者であり、消費者でもある。だから自分だけで経済サイクルが成立してしまう。ここには銭カネの立ち入るすきがない。自分の時間を売っても、それを自分で買いとっているからだ。時間系がひとりで独立しているのである。 これがガンディーのめざす「スワラージ(自治)」の実践だ。金を無用の長物にすることで、「時は金なり」を格言から虚言に格下げしてしまう。
しかしジャイナは自給自足にむかわず、むしろ小売業や金貸業といった貨幣経済にどっぷりとつかったような商売を営みながら、それでいて金や権力には無執着に暮らしている。こちらもかなりハイレベルな「矛盾の一致」といえそうだ。(2003.02.24記)
30.裸形のこと
西欧世界に「異能者=裸」という伝統はあるだろうか。
この方面はまだ不勉強なので、せいぜい聖フランチェスコや、イエス・キリストの磔刑画くらいしか思い浮かばない。ウィレム・デフォーがイエス役を演じていた映画「最後の誘惑」では、一糸まとわぬ完全なネイキドで、イエスが磔りつけになる場面があった。このシーンは時代考証をふまえてのものだというから、イスラエルでもやはり裸形のシンボルが生きていたに違いない。彼は政治犯として処刑されたわけだが、ここにもアウトサイダーと裸形の近しい関係がかいまみえる。
しかし、もともとイエスは東洋人であり、彼の磔刑だって東洋の事件といったほうがいい。やはり西洋には、地中海的な肉体美か、もしくは健康美としての裸しかないように思う。二十世紀の産物であるヌーディズムだってその延長であろう。ヌードとネイキドは、別物として考えるべきである。
裸形が異能者を象徴している社会というのは、インドのほかにアフリカがある。和田正平氏の「裸体人類学」によると、カメルーンのマンダラ山地では、鍛治職人を一種のシャーマンとみなしており、その異能者たるシンボルとして、彼らは裸形で製鉄するという。
インドでも、裸形はもともと通過儀礼のための「装束」か、シャーマンの象徴だったのかもしれない。しかし知性に裏打ちされたネイキドというのは、世界でもインドが特別のようである。古代ギリシア人たちは、ネイキドで歩くインドの修行僧たちを「裸の哲人」(ギュムノ・ソフィステース)とよんでいた。
その後カメルーンでは、西欧化の波にともない、着衣が義務づけられたという。それに従わない裸人たちは、憲兵隊によって牢獄にブチこまれてしまった。いわゆるカメルーン政府の「裸狩り」である。
中沢新一氏による「虹の階悌」に、チベット仏教のこんな戒めがある。
公衆の面前を裸で歩いたり、異常な行動をすることが
ヨーガ行者らしい振る舞いだと思い込む。でも、
それでは逆に人々の信頼は失われるものとなる。
思慮深くあること。これこそ、私の心からなる戒めだ
「異常な行動」というのは、このばあいヒンドゥーのサドゥーたちのように、地中に頭を埋めてみたり、いばらに寝っころがったりして、喜捨を求めることをいうのだろう。明らかにアウトサイダーっぽくふるまうことへの戒めに思える。
世界でいちばん裸にやかましいのはムスリムであろう。頭からすっぽりと黒服を覆い、目だけをギョロつかせているムスリム女性の姿はインドにも多かった。誰よりも、まず神にたいして醜い肉をみせるな、というのだからすごい。
ムスリムの帝王たちがインドに侵入したときも、ネイキドで街を歩くジャイナの姿にはオッタマげたにちがいない。ムスリムのインド支配がはじまると、さっそく裸形はご法度のひとつに数えられた。それからというもの、空衣派でも朱色か、白色の布をまとうのが慣習になったのだという。だからシュラバナ・ベルゴラの僧たちは、イスラム侵入前の伝統をいまでも守る、数少ない伝承者なのである。(2003.02.16記)
29.珊瑚の生活
たしかNHKの「海の生き物たち」といった番組だと思う。正月に見たのでほとんど記憶にないけれども、珊瑚の場面だけはよく覚えている。彼らの生態は一見したところ平和そのものといった印象だが、実は戦争にもひとしい熾烈なものだという。なかでも珊瑚どうしの縄張り争いにいたっては正視に耐えない映像であった。自らの消化器官を露出し、対手を溶解してしまうのだ。さらに夜間になると、ダメ押しとばかりにマダイが無差別に珊瑚を食い散らかしていく.....
これを見てすぐさま連想したのは、動植物学者デイビッド・アッテンボローの『植物たちの挑戦』だ。半ば眠っているかようにみえる植物の生態も、実は日照権の争いや、昆虫類を巻きこんだ種の保存戦略などで修羅場の連続だという。やっと競争に打ち勝ち、巨木に成長した木々でさえも、ゾウの大群になぎ倒されてジ・エンドである。
これらを見た後の印象は、当たり前といえばそうなのだが、「彼らには日曜日がない」ということであった。もし彼らにも週休一日でいいから余暇があり、命をおびやかされることなくのんびりした時間をもつことができれば、全く違う生き物になるんじゃないか。(2003.02.13記)
28.YMO
仕事がえりに駅前の新星堂に寄ったら、YMOワールドツアーの映像をがんがん流していて驚いた。なんと全アルバムが紙ジャケットでリリースされたという。うれしさのあまり一気にトランス状態に突入。7枚ほど買いこんでしまった。
権利が東芝EMIからソニーミュージックに移ったのが幸いしてか、1999年リリースのものより格段に音がよい。このピコピコ音は遺伝子レベルでインプリンティングされているだけに、音が出たら後はもうスレイブ状態である。しかも各アルバムに付属のインタビューがへたなマンガより面白く、土日は結局YMO一色でつぶれてしまった。わずかに『ぼくたちのアナ・バナナ』を観て涙したことが唯一の救いか。
ところで『増殖』のスネークマンショー、20年前のギャグに不覚にも笑ってしまった。Do you understand Mr.Ohira?(2003.02.03記)
27.ヴェイユのこと3
フランチェスコの「第二の誕生」は、全的な放棄によってはじめて達成された。そして裸形こそ、死と復活の儀式における古来からの「装束」なのだ。シャーマニズムにおいても、ちょうど「肉を脱ぎ捨てた骸骨」が裸形にうまく重なるではないか。その点では、イエスの磔刑も映画『最後の誘惑』のように裸形で描くべきであろう。
『トマス福音書』のなかでイエスはこう語る。
あなたがたが恥を取り去り、着物を脱ぎ、小さな子供たちのようにそれらを足元におき、踏みつけるとき(中略)、あなたがたは恐れることがないであろう(三七)
このグノーシス文書にみるイエスの言葉が、マハーヴィーラの伝えたかったことなのだと思う。ジャイナの修行僧たちは文字どおり、「着物を脱ぎ、小さな子供」のように無垢に、純粋に人生を生きぬこうとしているのだ。自分が、自分以外の何者でもなくなったとき、自分のソウルは裸んぼで生き生きして、生活すべてを「裸形化」していく。それは子供のように無時間性のなかを生きることであり、これこそが自由への道なのである。(2003.01.31記)
26.ヴェイユのこと2
ヴェイユとジャイナの共通性は、「逆創造(ディクリエーション)」という言葉に如実にあらわれている。これは創造の本質を「放棄」としてとらえるヴェイユ独特の表現だ。神の創造行為もまた逆創造であり、十字架を背負うイエスの姿もまたしかりである。つまり愛の本質も逆創造だというのである。
ジャイナの苦行(タパス)も、自虐的行為というよりむしろ逆創造としてとらえるべきであろう。苦行の本質とは全的な自己放棄である。その証しとして知られるのは、ゴーマティーシュヴァラのカヨトサガラ(立禅)の姿だ。
義人であるためには裸で、死んでいなくはならない。なんら想像上のことでなく。だから、義の模範となる人は、裸で、死んでいなくはならないのだ。(シモーヌ・ヴェイユ『重力と恩寵』)
またヴェイユによると、逆創造の実践は狂気の形をとるという。よって真に偉大な人物とは、狂人でなくてはならない。そしてまさに狂人こそ、「裸で死んでいる」状態で我々の前に姿をあらわす。聖フランチェスコの逸話もやはり、逆創造が神話化したものであろう。
彼フランチェスコにいったい何をおそれることがあろう。一言も発せず、彼は猛然としたあわただしさで衣服を脱ぎ去り、一枚また一枚と父の足元に投げやったのだ。衣服のことごとくである。ズボン下にいたるまで。おまけに、彼がちょうど持ち帰ってポケットに隠していた、例の呪われた財布も同様であった。今や彼は、生まれた日のように裸であった。第二の誕生に際して、彼はこの日、裸にもどったのである。(ジュリアン・グリーン『アシジの聖フランチェスコ』)
と、ここまで書いて、なぜヴェイユはジャイナについて何も書かなかったのか気になってきた。彼女はバガヴァット・ギータや仏教について多くを語っているだけに、なおさら謎ではないか。(2003.01.29記)
